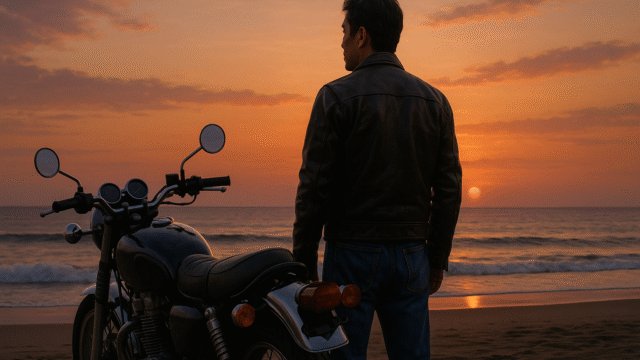リターンライダー驚愕!バイク10年の進化と変化
皆さん、こんにちは!おかぽんです。
前回の自己紹介記事では、40代・4児の父である私が、10年の時を経てリターンライダーとして再始動する決意をした経緯をお話しさせていただきました。(まだお読みでない方は、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです!) きっかけの一つとしてYouTubeの存在を挙げましたが、今回はそのあたりももう少し掘り下げつつ、リターンを決意した私が直面した「バイク界の10年間の変化」についてお話ししたいと思います。
さて、勢い込んで「バイクに乗るぞ!」と決意表明したのは良いものの、いざ具体的に情報収集を始めると、私はすっかり「浦島太郎状態」になっていることに気づかされました。
10年ひと昔、とはよく言ったものです。バイクの世界は、私が知っていた頃から、想像以上に大きく、そして深く変化していたのです。まるでタイムスリップしてきたかのような感覚。キラキラと輝く最新技術、昔はなかったジャンルのバイク、そして圧倒的な情報量…。
正直、「何から手をつければいいんだ…?」と途方に暮れかけた瞬間もありました。しかし、同時に、この未知なる新しいバイクの世界を探求することへのワクワク感も湧き上がってきたのです。
今回の記事では、私と同じようにブランクを経てバイクの世界に戻ってきた「浦島太郎ライダー」仲間や、これからバイクに乗ろうと考えている方に向けて、この10年間でバイクの世界がどのように変化したのか、そして私がどのように情報を集めているのか(特に、私を再びバイクの世界へと誘ったYouTubeチャンネルの影響も含めて)、私の驚きや戸惑いも交えながら共有していきたいと思います。
1. きっかけはYouTube! 情報の海と「サキヌマーのモトブログ」
まず最初に驚いたのが、バイクに関する情報量の多さと、その入手方法の多様化です。そして、何を隠そう、私のリターン熱に決定的に火をつけたのは、まさにこの現代的な情報収集手段の代表格、YouTubeでした。
私がSR400に乗っていた10年前。主な情報源といえば、バイク専門誌、メーカーのカタログ、そしてバイクショップの店員さんやバイク仲間の口コミくらいでした。雑誌を隅々まで読み込み、気になるバイクがあればショップに足を運んで実車を見る…そんな、ある意味でのんびりとした情報収集が主流だったように記憶しています。
ところが、今はどうでしょう。インターネット、特にYouTubeの存在感が圧倒的です。
前回の記事でも少し触れましたが、数あるモトブロガーさんの中でも、私が特に夢中になって、1年間ほぼ毎日見続けていたのが「サキヌマーのモトブログ」さんでした。
サキヌマ―さんは、様々なジャンルの最新バイクから少し前のモデルまで、次々と乗り換えながら、そのインプレッションを非常に分かりやすく、そして何よりめちゃくちゃ楽しそうに語ってくれます。プロライダーのような専門的すぎる解説ではなく、良い点も悪い点も(忖度なく?)正直に話してくれるスタイルが、私にはとても心地よかった。
動画で見るような、バイクの性能を限界まで引き出すアグレッシブな走り。正直に言って、40代リターンライダーの私自身が、あそこまでバイクを攻められるわけではありません。体力も技術も、そして度胸も(笑)。でも、「このバイクは本来こういう性能を持っているんだ」「限界付近ではこんな挙動をするのか」と、そのバイクが持つ本来のポテンシャルを知ることが、純粋に面白く、めちゃくちゃ勉強になったんです。「なるほど、だからこのバイクはこういう味付けなのか」とか、「この機能はこういう時に生きるのか」とか、まるで自分が試乗しているかのような感覚で、バイクへの理解が深まっていきました。
そして何より、サキヌマ―さん自身が本当にバイクが好きで、乗ることを心から楽しんでいる様子が、画面越しにビンビン伝わってくる。仲間とツーリングに行ったり、バイク談義に花を咲かせたりする姿を見ているうちに、「ああ、やっぱりバイクっていいな」「風を切って走るあの感覚、もう一度味わいたいな」「バイクを通じて、新しい世界を見てみたいな」という気持ちが、日に日に強くなっていったのです。
1年間、サキヌマ―さんの動画で様々なバイクのインプレッションを見続けていたら、もう「ただ見ているだけじゃ我慢できない!」「スペックや理屈じゃなく、自分で実際に乗ってみたい!」 という欲求が、どうしても抑えられなくなってしまいました。これが、私の10年ぶりのリターンを決定づけた、最大の理由と言っても過言ではありません。
もちろん、サキヌマ―さん以外にも、YouTubeには数えきれないほどのモトブログチャンネルが存在します。特定の車種に特化したチャンネル、ツーリングの美しい映像に特化したチャンネル、整備やカスタムに特化したチャンネル…。これらを活用すれば、バイクに関するありとあらゆる情報を、映像と音声で、非常に分かりやすく得ることができます。
一方で、情報の洪水に溺れてしまう危険性も感じています。あまりに多くのインプレッションを見すぎると、「結局、どのバイクが良いんだろう?」と逆に迷ってしまうことも。エンターテイメント性が高い動画も多く、その情報が必ずしも客観的・中立的とは限りません。
だからこそ、YouTubeで興味を持ったバイクについて、さらにブログや専門ウェブサイトで詳細なレビュー記事を読んだり、メーカー公式サイトで正確なスペックを確認したり、SNSで実際に乗っているオーナーの声を探したり、といった複合的な情報収集が重要だと感じています。昔ながらのバイク雑誌も、俯瞰的な視点や比較記事など、ネットにはない価値を提供してくれます。
この情報収集自体が、まるで宝探しのように面白く、リターン準備期間の大きな楽しみの一つになっています。
2. 技術の進化に唖然! バイクはもはやハイテクマシン?
情報収集を進める中で、最も衝撃を受けたのがバイク技術の劇的な進化です。私がSR400に乗っていた頃には考えられなかったような電子制御技術が、今や当たり前のように多くのバイクに搭載されています。(サキヌマーさんの動画でも、これらの技術がもたらす走りの違いがよく解説されていましたね)
- ABS (アンチロック・ブレーキ・システム): 今や多くのバイクで標準装備、あるいはオプション設定されているABS。急ブレーキ時などにタイヤがロックするのを防ぎ、車体の安定性を保ってくれる安全技術です。10年前も一部の大型バイクには搭載されていましたが、ここまで普及が進んでいるとは驚きました。特に、雨の日や砂が浮いた路面など、滑りやすい状況での安心感は絶大でしょう。私のSR400にはもちろん付いていませんでしたし、当時は「自分の腕でコントロールするもの」という意識が強かったですが、安全は何物にも代えがたい。リターンする上で、ABSの有無はバイク選びの重要なポイントになりそうです。
- トラクションコントロールシステム (TCS/トラコン): これも驚いた技術の一つ。アクセルを開けすぎた時などに、後輪が空転(スリップ)するのを抑制してくれるシステムです。特にパワーのあるバイクや、滑りやすい路面での発進・加速時に効果を発揮します。これも10年前は、レースマシンや一部の高性能バイクの装備というイメージでしたが、今ではミドルクラスのバイクにも搭載されるようになってきています。ABSと合わせて、ライダーのミスをカバーし、安全性を高めてくれる心強い味方ですね。
- 電子制御スロットル (ライド・バイ・ワイヤ): 従来のスロットルがワイヤーで物理的に繋がっていたのに対し、アクセル操作を電気信号に変換してエンジンを制御するシステムです。これにより、より緻密なエンジンコントロールが可能になり、後述するライディングモードの搭載にも繋がっています。最初は「ワイヤーじゃないとダイレクト感がないのでは?」と思いましたが、多くのインプレッションを見ると、違和感なく、むしろスムーズで扱いやすいという声が多いようです。
- ライディングモード: 電子制御スロットルなどの技術により、走行状況や好みに合わせてエンジン出力特性やトラクションコントロールの介入度などを切り替えられる機能です。例えば、「スポーツモード」では鋭いレスポンス、「レインモード」では穏やかな出力特性とトラコンの積極的な介入、といった具合です。1台で様々なキャラクターを楽しめるというのは、非常に魅力的ですね。
- LEDヘッドライト/灯火類: 昔のハロゲンランプに比べて、格段に明るく、消費電力も少なく、寿命も長いLED。デザインの自由度も高く、最近のバイクのシャープな顔つきはLEDによるところも大きいですね。夜間走行の視認性向上は、安全性に直結します。
- TFTフルカラー液晶メーター: スマートフォンのように高精細で多機能なメーターも増えました。速度や回転数だけでなく、燃費情報、ギアポジション、外気温、時計はもちろん、ライディングモードの表示、さらにはスマートフォンと連携して着信通知やナビゲーション情報を表示できるものまであります。もう、私が知っているバイクのメーターとは別次元です…。
- フューエルインジェクション (FI) の一般化: 私のSR400も後期型はFIでしたが、当時はまだキャブレター車も多く存在しました。特にSRはキックスタートだったので、エンジン始動にコツが必要なことも(それも味でしたが)。今のバイクはほぼFI化されており、季節や気温に関わらず、ボタン一つでスムーズにエンジンが始動するのは、やはり大きなメリットだと感じます。
これらの技術進化には、正直、ついていくのがやっとです。「そんなに電子制御に頼って大丈夫なのか?」「操作が複雑になるのでは?」という不安も少しあります。しかし、それ以上に、安全性の向上と快適性の向上というメリットは計り知れないと感じています。特に、10年のブランクがあり、体力にも若干の不安がある私のようなリターンライダーにとっては、これらの技術が大きな助けになることは間違いなさそうです。
3. トレンドも様変わり? 人気車種に見る時代の変化
技術だけでなく、人気を集めるバイクのジャンルやトレンドも、この10年で大きく変化したように感じます。(これもサキヌマーさんの動画などで、様々なジャンルのバイクに触れる中で実感しました)
- アドベンチャーバイクの隆盛: オフロードテイストのデザインに、長距離走行もこなせる快適性と積載性を備えたアドベンチャーバイクの人気が、世界的に高まっているようです。BMWのGSシリーズや、国内メーカーからもテネレ、アフリカツイン、Vストロームなど、様々なモデルが登場しています。舗装路も未舗装路も気にせず、どこまでも走っていけそうなタフなイメージは、確かに魅力的です。「バイクで旅をする」というロマンを掻き立てられますね。
- ネオクラシック/ヘリテイジモデルの充実: 一方で、私のような元SR乗りには嬉しい、クラシカルな雰囲気と現代的な走行性能を両立させたネオクラシック(またはヘリテイジ)と呼ばれるジャンルも人気を集めています。カワサキのZ900RS/Z650RS、ヤマハのXSRシリーズ、ホンダのGB350やホーク11など、各社から魅力的なモデルが登場しています。昔ながらのバイクらしいデザインを踏襲しつつ、ABSやFIといった現代の技術がしっかり搭載されているのは、リターンライダーにとって安心感があります。GB350などは、まさに現代版SRのようなポジションかもしれませんね。
- ミドルクラス(600cc~900cc)の活況: 昔は「ナナハン」という言葉に象徴されるように、大型バイクといえばリッタークラス(1000cc以上)が主流というイメージがありましたが、最近は600cc~900ccくらいの、いわゆる「ミドルクラス」が非常に元気な印象です。扱いやすいパワーと車格、十分な走行性能、そして比較的手頃な価格帯。このバランスの良さが、多くのライダーに支持されているのでしょう。ホンダのCBR650R/CB650R、ヤマハのMT-07/MT-09、スズキのSV650、カワサキのNinja 650/Z650など、各社から個性的なモデルが多数ラインナップされています。リターン後の最初のバイクとしても、有力な選択肢になりそうです。
- 400ccクラスの変化: 私が免許を取った頃は、400ccクラスは車検もあって中途半端、というイメージも少しありましたが、今はどうでしょうか。ホンダのCBR400Rや400X、カワサキのNinja 400/Z400など、魅力的なモデルもありますが、全体的に見ると、かつてのネイキッド百花繚乱時代(CB400SF、XJR400、ZRX400、インパルスなど)に比べると、ラインナップは少し寂しくなった印象も受けます。一方で、普通二輪免許で乗れる最大排気量として、その存在価値は依然として大きいですね。
もちろん、スーパースポーツやアメリカン、オフロードバイクなど、他のジャンルもそれぞれ進化を続けています。ただ、この10年というスパンで見ると、アドベンチャーとネオクラシックの台頭、そしてミドルクラスの充実ぶりが、特に目立つ変化だと感じました。
私の愛したSR400のような、シンプルで普遍的な魅力を持つバイクが惜しまれつつも生産終了となる一方で、時代に合わせて新しい価値観を持ったバイクが次々と生まれている。選択肢が増えたことは、嬉しい悩みですね。
4. ウェアやギアも進化! 安全とお洒落の両立?
バイク本体だけでなく、ヘルメットやウェア、グローブ、ブーツといったライディングギアも、この10年で大きく進化しているようです。(前回記事でも触れましたが、私は10年前に全て手放してしまったので、これから1から揃え直しです…!)
- 安全基準の浸透とプロテクターの進化: CE規格(欧州の安全基準)に適合したプロテクターが、ジャケットやパンツに標準装備、あるいはオプションで装着できるのが当たり前になってきています。胸部プロテクターの重要性も広く認識されるようになりました。素材や形状も進化し、より薄く、動きやすく、それでいて高い保護性能を持つものが増えているようです。
- デザイン性と機能性の両立: 昔は「安全性を重視すると、どうしてもゴツくて野暮ったいデザインになりがち」というイメージがありましたが、今は普段着としても着られそうな、お洒落なデザインのライディングウェアがたくさんあります。防水透湿素材、ベンチレーション機能、ストレッチ素材など、快適性を高める機能も格段に進歩しています。
- 電熱ウェアの普及: これは本当に驚きました。バッテリーで発熱する電熱グローブや電熱ベスト(インナージャケット)などが、かなり一般的になっているようです。これがあれば、冬の寒さもかなり軽減され、ツーリングシーズンが広がりそうですね。
まだ本格的にギア選びを始めたわけではありませんが、ざっと調べただけでも、その進化ぶりに目を見張るばかりです。安全性と快適性、そしてファッション性を高い次元で両立できるようになったのは、ライダーにとって非常に喜ばしいことですね。これもまた、じっくり時間をかけて、自分に合ったものを選んでいきたいと思っています。(このギア選びの過程も、今後のブログで詳しくレポートする予定です!)
まとめ:浦島太郎、大海を知る(そして、ワクワクする)
というわけで、今回はリターンライダーの私が、情報収集を通じて感じた「バイク界の10年間の変化」について、私をバイクの世界に引き戻したYouTubeチャンネル「サキヌマーのモトブログ」さんの影響にも触れながら、お話しさせていただきました。
情報収集の方法は劇的に多様化し(特にYouTubeの影響は絶大!)、バイクの技術は目覚ましく進化。人気のジャンルやトレンドも変わり、ライディングギアもより安全で快適に、そしてお洒落になっていました。
まさに「浦島太郎状態」だった私ですが、この変化を知ることは、決してネガティブなことではありませんでした。むしろ、知らないことがたくさんあるからこそ、これから知っていく楽しみがある。新しい技術やバイクに触れることへの純粋な好奇心と期待感が、今は不安を上回っています。サキヌマーさんの動画を見て高まった「自分も乗りたい!」という気持ちを、いよいよ実現させる時が来たのです。
もちろん、ブランクがあること、そして年齢的なことも考慮し、最新技術に過度に依存するのではなく、基本に忠実に、安全運転を第一に心がけるつもりです。
さて、バイクの世界の「今」を少し理解できたところで、いよいよ次は、私の新しい相棒となるバイク選び、そして安全なバイクライフに不可欠なギア選びへと進んでいきたいと思います。この浦島太郎ライダーが、数ある選択肢の中から、どんな一台を選び、どんな装備を揃えていくのか…。そのリアルな悩みや決断の過程も、このブログで包み隠さずお伝えしていく予定です。
皆さんは、この10年間のバイクの変化について、どのように感じていますか?「この技術は本当に便利だよ!」「リターンライダーなら、こういうバイク(ギア)がおすすめ!」といったご意見やアドバイスがあれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。情報交換を通じて、皆さんと一緒にこのリターンライダーライフを楽しんでいけたら最高です。
今回も長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もお楽しみに!